
楽しく自由な一人暮らし。でも家事は自分でしなくっちゃいけないし、金欠、急病や強引な勧誘などなど、トラブルの種も潜んでいる。対策を身に着けて、一人暮らしの楽しさを思いっきり楽しめる「一人暮らしの達人」になろう!
健康の基本は食生活。しかも、生活費の中で節約しやすいのが食費とくれば、自炊しない手はない。腕を磨けばモテるかも?
誰もが気になる家賃。部屋探しの条件ともなるので、しっかり決めよう。ポイントは、まず同じく毎月支払う共益費(管理費)と合わせて考えること。アンケートでは、5万円~6万円が26.8%と最多で、6万円以下が半数を占めることがわかった。
●カレー・シチュー
容器にビニール袋を入れて注ぎ、口をしばって冷凍(容器がよごれない!)
●揚げ物
キッチンペーパーで包んで電子レンジで加熱(油をカットできる!)
●野菜
少しかために茹でて下ごしらえしてから冷凍
●冷凍に向かないもの
レタスやキュウリなど水分の多い野菜、豆腐、チーズ
●肉
冷蔵庫で自然解凍。もしくは解凍機能付きの電子レンジで解凍
●洋風
コンソメはスープや炒めものの味付けに。オリーブオイルはパスタに!
●和風
和風の基本はだし。お味噌汁に、煮物に!
●中華風
中華の調味料は使うと一気に味が本格的に。
●万能!
和洋中、マルチに活躍する頼れる仲間!

冷凍食品でお手軽ホットサラダ
冷凍カボチャ、冷凍のから揚げを電子レンジでチン。塩、こしょう、マヨネーズで和えれば、あっという間にボリュームたっぷりのサラダに

ドレッシングでさっぱりヌードル
ゆでたうどんやそうめん、スパゲッティに野菜やツナをのせ、ドレッシングをかければ、サラダ仕立ての主食になる

蒲焼き缶でどんぶりゴハン
鍋に蒲焼きを入れて火にかけ、とき卵を入れ、卵とじにした状態でごはんにかける。腹ペコ時にも満足などんぶりモノ!
何かと出費が多くなる一人暮らし。何にどう使うかは自分次第。努力と工夫次第で好きなものに、より多くのお金を使えるのが醍醐味。
アルバイト情報誌『フロム・エー』調べによると、家賃・光熱費などの必要経費を除いた、大学生が自由に使えるお金の平均額は約3万9000円。そのお金の使い道のトップ5は、下表の通り。何かと物入りな一人暮らし。加えて、外食など友達付き合いにもお金がかかる。あふれる物欲をぐっとガマンして無駄遣いをなくし、少しでも有効にお金を使おう。
| 1位.飲食(外食) | 外食はお金がかかる。なるべく自炊生活を心がけよう。 弁当持参ならさらに節約できる。 |
|---|---|
| 2位.友達付き合い | 金欠を理由に誘いを断りたくない。 でも、食材を各自で持ち込んでお部屋パーティーなら安く上げられる。 |
| 3位.ファッション・ブランド | バーゲンやリサイクルショップをうまく利用して使いすぎに注意。 チープなものをチープに見せないセンスを磨きたい。 |
| 4位.雑誌・マンガ | 大きい図書館なら雑誌を閲読できる。発売日を少し過ぎれば古本屋で安く売っているものも。 友達同士で貸し借りするのもアリ。 |
| 5位. 音楽 | CDショップで視聴してから購入するのも手だ。 |
まず、1カ月だけでも家計簿をつけてみよう。レシートを保存して、何に使ったかノートに書き込むだけでOK!無駄な出費が何かわかるはず。
まず、1日に使える生活費を計算。1カ月の生活費から、家賃や光熱費などを引き、それを1カ月の日数で割る
1日の生活費を封筒に分け。毎日、その封筒のお金を財布に移し変える
お財布には決められた額があるだけ。無駄な買い物を防ごう
1日が終わったら、封筒に残ったお金は貯金箱に
待機消費電力をカット
コンセントにつなげているだけで電気代はかかっている。ボタンひとつで電源を切ってくれる省エネタイプのアタッチメントでタコ足配線も整理。
外食するときはクーポン券を利用
駅や書店で、タダでもらえるフリーペーパーには、10%オフやドリンクサービスなどの特典のあるクーポンがついている。これを利用しない手はない!
普通の汚れなら、洗濯機は時短
泥だらけというのでなければ、洗濯機は15分も回せば十分。洗濯機についている時短コースを使えば、電気代と水道代も半分に。
リサイクル精神で節約
本は古本屋、家具は市町村のリサイクルセンターで買えば安く抑えられる。不用になったものは、売ればお部屋の整理整頓にもちょうどいい
一人暮らしがつらくなるのは、なんといっても病気になったとき。普段の生活習慣から、病気にならないよう気をつけよう
楽しく大学生活を過ごすためには、基礎体力が命。睡眠を十分とり、栄養バランスの良い食事を心がけ、適度な運動で汗を流す……といった生活が理想的。こういう規則正しい生活を続けていれば、バイト、サークル、勉強と忙しい毎日も乗り切れるはず。それでも体の調子が悪いなと感じたら、無理をせず、体を温めて、ぐっすり眠ろう。頼れる人間がすぐそばにいないからこそ、自己管理が重要だ。
最近は、アトピーに代表される皮膚アレルギーなど、アレルギーのある人は増加傾向にあるらしい。その理由は大きく分けて3つ。ストレスの増加、ダニなどが発生しやすい住環境、そして食生活の変化だ。ここでは、快適に暮らせる住まいの条件を考えてみよう。敵は、室内のホコリ、カビ、ダニなど。こうした悪玉を取り除くことが、住まい選びの絶対条件になる。また、ぐっすり眠るために、静かな環境かどうかも重要。周辺に騒音施設がないか、休日の昼間だけでなく、夜間、平日もチェックしたい。
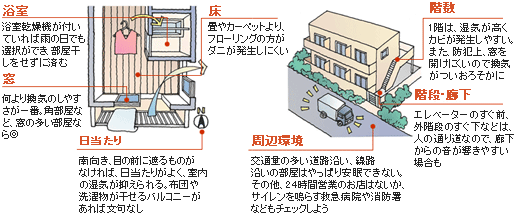
風邪をひいたり、おなかの調子が悪かったり……、急に体調を崩した場合、家に薬のひとつもないと不安でしょうがないはず。備えあれば憂いなし。
・緊急病院の連絡先
・薬など救急箱
・遠隔地保険証
(保護者に上京前に申請してもらおう。この保険証がないと、診察や薬代が実費になってしまう)
・風邪薬
・鎮痛剤
・絆創膏
・体温計
・冷却シート
せっかくならいつでも友達や恋人を呼べるくらい、部屋をキレイにしておきたい。そのためには気づいたときにささっと掃除する習慣が大事!
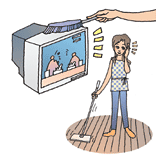
汚れをためればためるほど掃除が大変になるのは当然のこと。だから、掃除を一番簡単に済ませる方法は、汚れがひどくならないうちに手を打つこと。
休日にまとめてやろうなんて思わずに、テレビを見ながら、電話をしながら、ハンディモップや、くるくるクリーナーで、気づいたところをささっと掃除しよう。そのためには、こうした掃除用具を、普段目の届きやすいところに置いておくのも重要。
特に汚れがつきやすいキッチン・バス・トイレは注意!例えばキッチンなら、キッチンペーパーを用意して、コンロやレンジのまわりに調味料や油が飛び散ったら、すぐにふき取ろう。シンクの中は、食器洗いの終わったスポンジでささっとこするだけでOK。トイレも、水に流せる紙製のクリーナーでふき取ればOK。お風呂は入浴後にさっと浴槽を洗い流しておく。
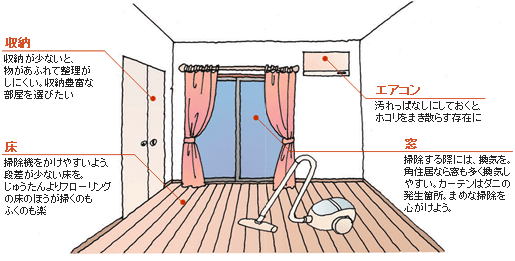
ゴミ出しのマナーを守ることは、大人の第一歩。分別のルールだけでなく、「前の日に出さない」「収集日を守る」ことも、最低限のマナー。また、行政区によって分別の仕方が違うので、大家さんや行政区の役所にしっかり聞いておこう!
●燃やすゴミ
汚れた紙、布、汚れのとけないプラスチック
●燃えないゴミ
せともの、ガラス容器、電球、金具など
●古紙
新聞、雑誌、ダンボール、包装紙や紙袋など
●有害ゴミ
乾電池、体温計、スプレー缶、蛍光灯
●資源ゴミ
ペットボトル、マークのついているプラスティック容器。ただし汚れているものは×
6畳+バス+キッチンが、一人暮らしの平均的な住まい。だから収納スペースも限られている。ココは収納術を勉強して、少しでも部屋を広々使いたい!

本、雑誌、洋服、靴etc. 最初はたいしたことがなくても、荷物は生活していくうちにどんどん増えていくのが常。それなのに、一人暮らしのお部屋は、収納量も限られているので、収納には工夫が必要。しかし、「物を増やさない」「置かない」という暮らし方も重要。例えば本やCDは図書館で借りれば、お金の節約にもなる。冬の衣類や毛布などかさばるものは、夏場には実家で保管して。
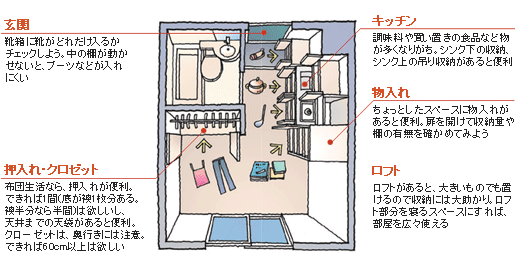
同じ収納スペースでも、しまい方、たたみ方を工夫すれば収納量もぐんとアップ!まずはついついあふれがちな雑誌、洋服、靴の収納をマスターしよう!
雑誌は必要なページだけカットし、スクラップブックに貼ったり、クリアファイルに保存。残りは捨ててしまおう。
押入れ下段にはキャスターつきのケースを使い、手前にオンシーズン、奥にオフシーズンのものを収納すれば入れ替えもカンタン。
靴箱にしまうと、収納しやすいが、中身が把握しにくいのが難点。そんなときは靴箱の側面に、靴の写真を貼っておけば、一目瞭然。
空き巣やのぞき、強引な勧誘やセールスなど、一人暮らしは楽しい半面、トラブルに巻き込まれる危険も増える。部屋選びと暮らし方で自分の身は自分で守ろう。
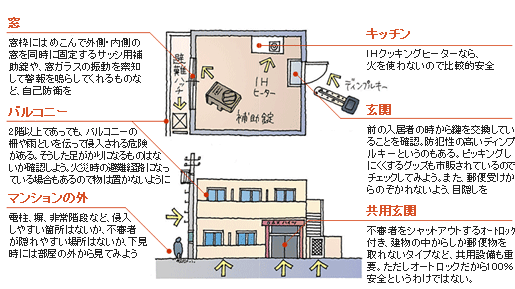
急病、水漏れ、鍵の紛失、落とし物etc.一人暮らしはトラブルがいっぱい。いざというときに対応してくれる窓口をチェックしておこう。何かあったらすぐ連絡できるように、携帯のメモリーに登録するのも手。また、大家さん、管理会社、保護者の勤務先、近くの救急病院などの連絡先は事前に調べて、いざというときにすぐわかるようにしておこう。
・不動産に関するトラブル
東京都)東京都都市整備局 住宅政策推進部不動産業課 指導相談係 03(5320)5071
大阪市)大阪市立 住まい情報センター 06-6242-1177
・消費生活に関しての相談
例えば、国民生活センター 03(3446)0999
・強引な新聞勧誘に対する苦情
例えば、新聞セールスインフォメーションセンター
東京都)03(3575)0801
大阪)06(6341)4161
福岡)092(771)6330
・電車や駅に忘れ物をした
鉄道会社の忘れ物の取扱所に連絡してみよう!
(※他にも、医療や安全については都道府県や市町村に相談窓口が設けられていることが多い。確認してみよう)
